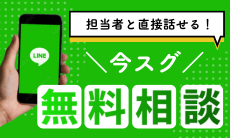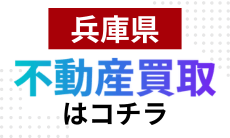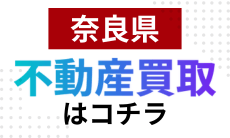兵庫県 地域格差が目立つ空き家問題
あなたの隣も?兵庫県で過去最多39万戸の衝撃。
データと事例で探る「空き家問題」の深刻なリアルと未来への処方箋
「うちの近所にも、何年も誰も住んでいない家があるな…」
そう感じたことはありませんか?
今、兵庫県で「空き家」が静かに、しかし確実に増え続け、地域社会の未来を揺るがす大きな問題となっています。
2024年に公表された最新データによると、県内の空き家数は過去最多の約39万戸に達しました。
これは、県内の住宅の約8軒に1軒が空き家であることを意味します。
この問題は、過疎地の話だけではありません。
都市部でも深刻化し、景観の悪化や治安への不安、さらには地域の活力を奪う要因となっています。
この記事では、衝撃的な最新データから兵庫県の空き家のリアルを紐解き、
なぜ問題がここまで深刻化するのか、その背景にある根深い要因を分析します。
さらに、この困難な課題に立ち向かう行政や民間・コミュニティの挑戦、
そして私たちが未来のために今できることを、具体的な事例を交えながら探っていきます。
これは、決して他人事ではない、私たち全員で向き合うべき物語です。
衝撃の事実:データが語る兵庫県の「空き家」のリアル
言葉だけでは、この問題の深刻さは伝わりません。
まずは、公的なデータが示す兵庫県の揺るぎない事実を見ていきましょう。
総務省が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」。
その令和5(2023)年調査の速報値は、私たちに厳しい現実を突きつけました。
兵庫県の空き家数は38万6900戸。
前回調査(2018年)から2万6700戸も増加し、過去最多を更新したのです。
空き家率も13.8%と高止まりが続き、問題の悪化に歯止めがかかっていません。
さらに深刻なのが、県内における「地域格差」です。
地図を広げると、問題の偏在がはっきりと見えてきます。
- 但馬地域: 21.2%
- 淡路地域: 23.8%
- 西播磨地域: 19.0%
これらの地域では、実に5軒に1軒以上が空き家という異常事態に陥っています。
市町別に見ると、その深刻さはさらに増します。
県内で最も空き家率が高いのは佐用町で31.4%。次いで相生市が27.2%、淡路市が26.9%、養父市が26.4%と続きます。
県境の山間部や離島地域で、コミュニティの維持すら危ぶまれる状況が生まれているのです。
「それは過疎地の話でしょう?」と思うかもしれません。
しかし、都市部も決して例外ではないのです。
県庁所在地である神戸市に目を向けてみましょう。
市全体の空き家率は13.1%と県平均よりは低いものの、区ごと見ると様相は一変します。
特に神戸市兵庫区の空き家率は24.7%と、県内のどの市町よりも高い水準に迫る勢いで突出しています。長田区(17.5%)も高い水準です。
このように、データは兵庫県が抱える空き家問題の「量」と「地域的な偏り」を明確に示しています。
では、なぜこれほどまでに空き家は増え続けてしまうのでしょうか。
なぜ空き家は増え続けるのか?3つの根深い要因
空き家問題は、単一の原因で発生するわけではありません。
社会構造の変化、地域固有の歴史、そして個人の経済的な事情。
これら複数の要因が複雑に絡み合い、問題を根深くしています。
第1の要因:避けられない人口の波
最大の要因は、日本全体が直面する「人口減少」と「超高齢化」です。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、兵庫県の世帯数は2025年から2045年までの20年間で約17万世帯も減少すると予測されています。
住宅の総数が変わらなければ、この減少分がそのまま新たな空き家予備軍となるのです。
特に、高齢の親が施設に入所したり、亡くなったりした後、実家が空き家になるケースは後を絶ちません。
子どもたちはすでに独立して別の場所に家を構えているため、実家に戻る選択肢はなく、結果として誰も住まない家が残されていきます。
第2の要因:地域に刻まれた「固有の事情」
マクロな人口動態に加え、それぞれの地域が持つユニークな歴史や地理的条件が、空き家問題をさらに加速させています。
例えば、県内で突出して高い空き家率を示す神戸市兵庫区。
この地域の問題の背景には、「再建築不可」という物理的な制約があります。
戦後の復興期や高度経済成長期に形成された市街地には、現在の建築基準法が定める「幅4メートル以上の道路に2メートル以上接する」という接道義務を満たさない土地が多く存在します。
こうした土地では家を建て替えることができず、リフォームにも多額の費用がかかるため、買い手が見つからず、結果的に放置されてしまうのです。
また、西播磨地域の相生市では、地域の産業史が影を落としています。
かつて造船業で栄えた時代、多くの労働者のために長屋形式の社宅が数多く建てられました。
しかし、産業構造の変化と共にこれらが老朽化。
さらに、建物が複数の所有者で権利を共有する「区分所有」であるため、全員の合意がなければ改修も解体もできず、身動きが取れないまま空き家として朽ちていくケースが多発しています。
第3の要因:相続と税金という「厄介な問題」
個人のレベルでも、空き家を放置せざるを得ない「厄介な事情」が存在します。
その代表が「相続」と「税金」です。
2024年4月に義務化されるまで、不動産を相続しても登記の変更は任意でした。
そのため、相続登記がされないまま何代も放置され、いざ売却しようとした時には相続人が数十人に膨れ上がり、もはや誰が本当の所有者か分からない「所有者不明土地」となってしまうケースが少なくありません。
さらに、固定資産税の仕組みも問題を複雑にしています。
住宅が建っている土地は「住宅用地特例」により、税金が最大で6分の1に軽減されます。
老朽化した家を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、税金が何倍にも跳ね上がってしまうのです。
このため、「使う予定はないけれど、税金のために解体せず放置しておく」という所有者が後を絶ちません。
しかしその一方で、空き家の維持管理には年間数十万円の費用がかかり、所有者にとって大きな経済的負担となっているのもまた事実です。
「負の遺産」から「未来の資源」へ!兵庫の挑戦と希望の光
深刻化する一方に見える空き家問題ですが、この困難な課題に立ち向かい、空き家を「負の遺産」から「未来への資源」へと転換させようとする力強い動きが、兵庫県内各地で始まっています。
行政の挑戦:「守り」と「攻め」の施策
兵庫県や各市町は、問題解決のために「守り」と「攻め」の両面から対策を強化しています。
「守り」の施策としては、まず「空き家バンク」や専門家と連携した相談窓口を設置し、所有者と利用希望者のマッチングや、法務・税務に関する相談体制を強化。
そして、周辺に危険を及ぼす「特定空家」に対しては、所有者に助言や指導を行い、改善が見られない場合は行政代執行による強制解体も辞さないという厳しい姿勢で臨んでいます。
実際に神戸市などでは、所有者不明の危険な空き家を行政の費用で解体した事例も出てきています。
一方、「攻め」の施策も活発です。
空き家を住宅や店舗、地域交流拠点として改修する費用を補助する「空き家活用支援事業」は、その代表例です。
若者や子育て世帯には補助率を上乗せするなど、移住・定住促進と絡めた工夫も見られます。
さらに、県独自の「空家活用特区制度」を設け、通常は建物の用途変更が難しい市街化調整区域でも、空き家をレストランや宿泊施設として活用できるよう規制を緩和しています。
希望の光:地域で輝く民間・コミュニティの力
行政の取り組み以上に希望を感じさせるのが、地域の実情を熟知したNPOや民間企業、そして地域住民による創造的な活動です。
- 丹波篠山市の挑戦: NPO法人「集落丸山」は、茅葺き屋根が美しい古民家を改修し、レストランや一棟貸しの宿として再生。
単体の施設としてだけでなく、地域全体で観光客をもてなす「集落丸ごとホテル」という先進的なモデルを構築し、国内外から注目を集めています。 - たつの市の奇跡: 城下町の風情が残るたつの市では、市民が出資して設立したまちづくり会社「株式会社 緑葉社」が、使われなくなった町家や醤油蔵など約80棟の遊休不動産を再生。
新たにカフェや雑貨店など40もの店舗を誘致し、一度はシャッター街となりかけた通りに新たな賑わいを生み出しています。 - 神戸市の多様な試み: 大都市・神戸でも、NPO法人が空き家をリノベーションし、経済的に困難を抱えるひとり親世帯向けの支援住宅として安価に提供したり、地域住民が集うコミュニティガーデンとして活用したりと、社会的な課題解決につなげる動きが広がっています。
これらの事例は、空き家が単なる厄介者ではなく、アイデアと情熱次第で、地域の魅力を再発見し、新たな価値を創造するための「宝の原石」になり得ることを力強く示しています。
私たちの未来のために。今、考えるべきこと
空き家問題は、一朝一夕に解決できる魔法の杖が存在しない、非常に複雑で根深い課題です。
多様な対策が進む一方で、まだ多くの課題が残されています。
施策が本当に効果を上げているのかを測る客観的な指標(KPI)が不足している点や、2024年4月から始まった相続登記義務化だけでは、資産価値の低い土地の所有者不明問題を根本的に解決できない可能性などが指摘されています。
また、活発な不動産市場が残る都市部と、人口減少が著しい過疎地域とでは、有効なアプローチは全く異なります。
空き家率が低い播磨町のように、新たな住民の転入によって中古住宅市場が自然に循環している地域もあれば、佐用町のように、行政による強力な介入や、外部からの大胆な投資がなければ状況の改善が難しい地域もあります。
画一的な対策ではなく、それぞれの地域特性に応じたオーダーメイドの処方箋が不可欠です。
では、私たち一人ひとりに何ができるのでしょうか。
まずは、この問題に関心を持つことです。
この記事をきっかけに、ご自身の住むまちの空き家率や、どんな対策が行われているのかを調べてみてください。
そして、もしご自身が空き家を所有する当事者、あるいは将来その可能性があるのなら、問題を先送りにせず、できるだけ早く自治体の窓口や専門家に相談することが重要です。
空き家問題は、単なる「個人の財産管理の問題」ではありません。
地域の安全、景観、経済、そしてコミュニティそのものの持続可能性に関わる、「私たち全員の社会問題」です。
未来の世代に、活気と魅力あふれる兵庫県を残していくために。
今こそ、私たち一人ひとりが当事者意識を持ち、この課題に真剣に向き合う時が来ています。
兵庫県神戸市内全域/尼崎市/西宮市/芦屋市/伊丹市/宝塚市/川西市/三田市/明石市など
株式会社Go不動産(ゴーフドウサン)は、どんな物件でも買取りや売却のご相談承ります!
不動産でお困りの方はご連絡下さい!
株式会社Go不動産
TEL:06-6155-4564 / FAX:06-6155-4566
MAIL:info@go-fudosan.com