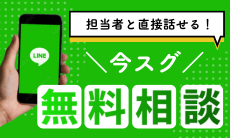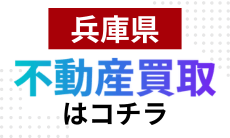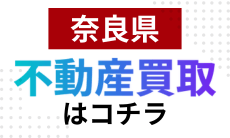借地権とは
借地権とは?基本から売買、相続、トラブルまで解説
借地権付き建物。
所有権付きの物件に比べて初期費用を抑えられる可能性がある一方、その権利関係は複雑で、特有のルールやコストが存在します。
この記事では、「借地権」とは何かという基本的な概念から、その種類、メリット・デメリット、売買や相続、そして地主との間で起こりがちなトラブルまで、借地権の全体像を解説していきます。
借地権の基本:所有権との決定的な違い
借地権とは、一言で言えば「建物を所有する目的で、地主から土地を借りる権利」のことです(借地借家法第2条)。
土地の所有権そのものを買うのではなく、あくまで土地を借りる権利と、その上に建っている「建物」を所有する、という二重構造になっています。
所有権との最大の違いは、土地の所有者が地主であるという点です。
これにより、以下のような特徴が生まれます。
- 土地の固定資産税・都市計画税は地主が支払う。
- 借地権者は地主に対して毎月「地代」を支払う義務がある。
- 建物の建て替えや売却には、原則として地主の承諾が必要になる。
つまり、初期費用を抑えられる代わりに、地代の支払いや地主の意向といった制約の中で建物を所有するのが借地権の基本構造です。
借地権の主要な種類:契約時期で変わるルール
借地権は、契約が結ばれた時期によって適用される法律が異なり、権利の内容が大きく変わるため、注意が必要です。
境目となるのは1992年8月1日です。
1. 旧借地権(1992年7月31日以前の契約)
旧法は、一度土地を貸すと半永久的に返ってこないと言われるほど、借主(借地権者)の権利が非常に強く保護されていました。
- 存続期間:堅固な建物(鉄筋コンクリート造など)で60年、非堅固な建物(木造など)で30年と定められているが、更新が原則。
- 更新:地主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要ですが、これが非常に厳格に解釈されるため、事実上、借主が望む限り半永久的に更新が可能でした。
現在も旧法で契約された借地権は、更新後も旧法が適用されます。
2. 新借地権(1992年8月1日以降の契約)
旧法の問題点を解消し、土地の有効活用を促すために施行されたのが「借地借家法」です。
新法では、更新がある「普通借地権」と、更新がなく必ず土地が返還される「定期借地権」が創設されました。
- 普通借地権
- 存続期間:当初30年以上。
- 更新:1回目の更新で20年、2回目以降は10年。
旧法と同様に、地主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要ですが、旧法よりは要件が緩和されています。それでも借主の権利は強く守られています。
- 定期借地権 更新がなく、契約期間の満了とともに土地を更地にして地主に返還することが確定している借地権です。これにより地主は安心して土地を貸し出せるようになり、分譲マンションなどで広く活用されています。
主に以下の3種類があります。- 一般定期借地権:存続期間50年以上。
用途制限はなく、居住用・事業用どちらも可。契約終了時は建物を解体し、更地で返還します。 - 事業用定期借地権等:存続期間10年以上50年未満。
事業用の建物に限定されます。コンビニやロードサイド店舗などで利用されることが多いです。 - 建物譲渡特約付借地権:存続期間30年以上。
契約終了時に、地主が建物を相当の対価で買い取る特約が付いています。
- 一般定期借地権:存続期間50年以上。
借地権のメリット・デメリット
借地権は、土地を借りる「借地権者」と貸す「地主」、双方にメリットとデメリットがあります。
借地権者(借りる側)の視点
- メリット:
- 初期費用の安さ:土地代が不要なため、所有権付き物件に比べ購入価格が安い(一般的に所有権の6〜8割程度)。
- 税負担の軽減:土地の固定資産税・都市計画税の納税義務がない。
- デメリット:
- 地代の支払い:毎月、地代というランニングコストが発生する。
- 各種制約と承諾料:建物の建て替え(増改築)や売却には地主の承諾が必要で、その際に「承諾料」を支払うのが一般的。
- 住宅ローンが借りにくい:土地を担保にできないため、金融機関によっては住宅ローンの審査が厳しくなる傾向がある。(各金融機関に確認が必要)
- 資産価値:所有権に比べ、資産価値は低く評価されがち。
地主(貸す側)の視点
- メリット:
- 安定収入:土地を所有したまま、長期にわたり安定した地代収入を得られる。
- 一時金収入:更新時や承諾時に、更新料や承諾料といった一時的な収入が期待できる。
- 管理負担の軽減:土地の管理は基本的に借地権者が行うため、管理の手間が少ない。
- デメリット:
- 利用の制限:一度貸すと、長期間にわたり土地を自由に利用できない(特に普通借地権)。
- 収益性のリスク:固定資産税や物価の上昇に対して地代の値上げがスムーズに進まない場合、収益性が悪化するリスクがある。
- トラブルのリスク:借地権者との間で、地代の値上げや更新、承諾を巡るトラブルが発生する可能性がある。
お金の話:地代・更新料・承諾料の相場
借地権に関わる金銭は、法律で明確に定められていない「慣習」によるものが多く、当事者間の関係性が大きく影響します。
- 地代:明確な算定式はありませんが、一般的に「土地の固定資産税評価額の3~5倍」や「更地価格の年1~2%程度」が目安とされます。
- 更新料:法的支払い義務はありませんが、契約書に記載がある場合や、長年の慣習として支払われることがほとんどです。相場は「更地価格の3~5%程度」とされています。
- 各種承諾料:
- 建替承諾料(増改築承諾料):建て替えや大規模リフォームの際に支払う承諾料。相場は「更地価格の3~5%程度」。
- 譲渡承諾料(名義変更料):借地権付き建物を第三者に売却する際に支払う承諾料。相場は「借地権価格の10%程度」と高額になることが多く、注意が必要です。
売買・相続する際の重要ポイント
借地権の権利が移転する「売買」と「相続」では、手続きと注意点が大きく異なります。
売買
借地権付き建物を売却する場合、地主の承諾が不可欠です。
承諾なしに売却しても、新しい買主は地主に対して権利を主張できません。
- 地主への事前相談・承諾の取り付け
- 譲渡承諾料の支払い交渉
- 売買契約の締結
- 登記手続き
地主が正当な理由なく承諾しない場合は、裁判所に申し立てを行い、地主の承諾に代わる許可を求める「借地非訟」という手続きもあります。
相続
売買と異なり、法定相続人が借地権を相続する場合、地主の承諾や承諾料は不要です。
相続は権利の包括的な承継であり、譲渡(売買)とは見なされないためです。
ただし、相続が発生したことは地主に通知しておくのがマナーです。
注意すべきは、相続人以外の人に遺言で財産を渡す「遺贈」の場合です。
このケースは売買と同様に扱われ、原則として地主の承諾と承諾料が必要になります。
よくあるトラブルと解決策
地主と借地権者の関係は長期にわたるため、様々なトラブルが起こり得ます。
- 地代の値上げトラブル:地主から周辺相場や税額の上昇を理由に地代の値上げを請求されるケース。
まずは話し合いでの合意を目指しますが、まとまらない場合は裁判所の調停や訴訟に発展することもあります。 - 更新拒絶トラブル:普通借地権の更新時に、地主から「自分で使いたい」などの理由で更新を拒絶されるケース。
地主側には、借地人が土地を必要とする事情を上回るほどの「正当事由」が求められ、多くの場合、立退料の提供が必要となります。 - 無断増改築トラブル:地主に無断で建物を建て替えたり、大規模な増改築を行ったりすると、契約違反と見なされます。
これが地主との「信頼関係を破壊する」と判断された場合、契約を解除される可能性があります。
これらのトラブルを避けるためには、日頃から地主との良好な関係を築き、契約書の内容をよく確認し、何かを行う前には必ず相談することが重要です。
万が一トラブルになった場合は、一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
借地権は、所有権とは異なる独特の権利形態です。
初期費用を抑えて好立地に住めるという大きなメリットがある反面、地代の支払いや地主の承諾が必要といった制約も伴います。
特に、1992年を境にルールが大きく異なる「旧法」と「新法(普通・定期)」の違いを理解することは不可欠です。
売買や相続、更新の際には思わぬ費用や手続きが発生することもあります。
借地権付き建物の購入や売却、あるいは相続を検討する際は、その物件に適用される法律や契約内容を十分に確認し、不動産会社や弁護士といった専門家の助言を得ながら、慎重に進めるようにしましょう。
借地権付き建物の売却相談はGo不動産にお任せください!
大阪府
大阪市24区(住吉区 此花区 平野区 西淀川区 福島区 港区 都島区 西成区 中央区 天王寺区 大正区 浪速区 淀川区 生野区 阿倍野区 東淀川区 住之江区 城東区 東成区 東住吉区 旭区 北区 西区 鶴見区)
堺市7区(北区 東区 堺区 南区 中区 美原区 西区)
その他/箕面市 摂津市 忠岡町 和泉市 豊中市 泉大津市 寝屋川市 藤井寺市 柏原市 岸和田市 大東市 羽曳野市 岬町 高槻市 門真市 泉南市 吹田市 島本町 泉佐野市 阪南市 茨木市 八尾市 東大阪市 枚方市 交野市 高石市 四條畷市 富田林市 守口市 松原市 池田市 大阪狭山市 貝塚市 河内長野市など