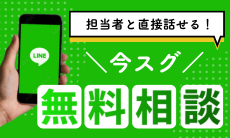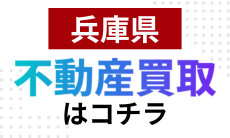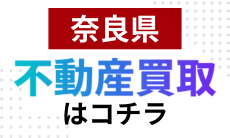相続登記の義務化について
【2024年4月1日施行】
相続登記義務化
法律の趣旨から罰則、新制度までを解説
2024年4月1日資産管理に深く関わる法改正「相続登記の義務化」を定めた改正不動産登記法が施行されました。
これは単なる手続き上の変更ではありません。
日本が抱える社会問題の解決を目指す意思が込められた重要な法改正です。
これまで任意とされてきた相続登記が、なぜ今「義務」となったのか。具体的に何を、いつまでに行う必要があるのか。もし怠った場合、どのようなリスクがあるのか。
この記事では、法改正の背景から、具体的な義務の内容、罰則、そして新たに設けられた救済措置である「相続人申告登記」制度まで、関連する法令を基に解説します。
ご自身の、そしてご家族の大切な資産を守るため、この機会に法律の趣旨を正しく理解しましょう。
なぜ相続登記は義務化されたのか?―法改正の背景と目的
相続登記の義務化は、突如として始まったものではありません。その根底には、社会問題となっている「所有者不明土地問題」という深刻な課題が存在します。
所有者不明土地問題とは、不動産登記簿上の所有者名義が長年変更されず、亡くなった方や過去の住所のままになっていることで、現在の本当の所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地のことです。
この面積は年々拡大し、国土交通省の調査では、九州本島の面積(約367万ha)を上回る約410万haに達すると推計され、経済活動や社会インフラの整備など各方面に多大な影響を及ぼすものと考えられます。
具体的には、以下のような問題を引き起こします。
- 公共事業の阻害:道路拡張やインフラ整備のための用地買収が進まない。
- 災害復旧の遅延:災害発生時に、土地所有者の同意が得られず復旧作業に着手できない。
- 民間取引の停滞:所有者が不明なため、不動産の売買や有効活用ができない。
- 周辺環境の悪化:管理不全となり、雑草の繁茂や不法投棄の温床となる。
こうした状況を改善し、所有者不明土地の「発生予防」と「解消」を両輪で進めるために、今回の法改正が行われました。その核心が、相続登記の義務化です。土地の所有権に関する情報を最新の状態に保つことで、土地の利用価値を最大化し、国民経済の健全な発展に寄与することを目指しているのです。
【条文から読み解く】相続登記義務の具体的な内容
では、法律は私たちに何を求めているのでしょうか。
改正不動産登記法の条文を基に、義務の「誰が・何を・いつまでに」を正確に見ていきましょう。
基本的な義務(不動産登記法第76条の2第1項)
(所有権の登記の申請の義務)
第七十六条の二
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
これを分解すると、以下のようになります。
- 義務を負う人(誰が?)
- 相続または遺贈によって、不動産の所有権を取得した相続人。
法定相続分で相続した人だけでなく、遺言によって不動産を取得した相続人も含まれます。
- 相続または遺贈によって、不動産の所有権を取得した相続人。
- 義務の対象(何を?)
- 日本国内にある、所有権の登記がされている全ての不動産(土地・建物)です。
- 義務の期限(いつまでに?)
- 「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」と定められています。
この「起算点」の解釈が非常に重要です。- 「相続の開始があったことを知った日」とは、一般的には被相続人が亡くなった事実を知った日を指します。
- 「所有権を取得したことを知った日」とは、その死亡の事実と、自分がその不動産を相続する権利を得たことを認識した日です。
遺言書が後から見つかった場合などは、その発見日が起算点となることもあります。
- 「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」と定められています。
遺産分割が成立した場合の特則(同条第2項)
しかし、相続人が複数いる場合、3年以内に遺産の分け方(遺産分割協議)がまとまらないケースも少なくありません。
そのための特例が設けられています。
2 前項の規定は、遺産の分割の協議又は遺言による遺産の分割の方法の指定がされ、これにより所有権を取得した者が、当該遺産の分割の日から三年以内に、その内容に応じた登記を申請することを妨げない。
これは、まず法定相続分で相続登記をするか、後述する「相続人申告登記」をしておけば、遺産分割協議が成立した日から改めて3年以内に、その協議内容に基づいた登記を申請すれば良い、という二段階の仕組みを認めるものです。
これにより、相続人間の話し合いに時間を要する場合でも、柔軟に対応することが可能になります。
【重要】過去の相続への遡及適用
この義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます(改正法附則第5条第6項)。
「何十年も前の祖父名義の土地が…」といったケースも、もはや放置できません。
この場合の期限は、以下のいずれか遅い日までとなります。
- 施行日である2024年4月1日から3年後(=2027年3月31日)
- 自身が不動産を取得したことを知った日から3年後
過去の相続に心当たりがある方は、まずは2027年3月31日を一つの目標として、準備を進める必要があります。
義務を履行しない場合のリスク―「過料」という制裁
義務がある以上、それを履行しない場合にはペナルティが伴います。
改正不動産登記法は、その制裁として「過料」を定めました。
10万円以下の過料(不動産登記法第164条第1項)
第百六十四条
第七十六条の二第一項(中略)の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
「正当な理由」なく期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。
ここで重要なのは、これが刑事罰である「罰金」とは異なり、行政上の秩序罰であるという点です。
前科が付くことはありませんが、法律上の義務違反に対する金銭的な制裁であることに変わりはありません。
過料が科されるまでのプロセス
登記を忘れたら即座に過料が科される、というわけではありません。手続きは段階的に進められます。
- 登記官による催告:まず、法務局の登記官から、申請義務者に対して登記をするよう「催告」の通知が送られます。
- 弁明の機会:通知には相当の期間が定められており、その期間内に登記を申請すれば過料は科されません。
また、「正当な理由」がある場合は、その旨を弁明する機会が与えられます。 - 裁判所への通知と決定:催告に応じず、かつ正当な理由も認められない場合に、登記官から地方裁判所にその事実が通知され、裁判所の判断によって過料の金額が決定されます。
「正当な理由」とは?
法律に具体的な定義はありませんが、法務省の通達などでは、以下のようなケースが「正当な理由」に当たると考えられています。
- 数次相続(相続が何度も重なること)が発生し、相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本の収集や相続人の特定に多大な時間を要する場合。
- 遺言の有効性や遺産の範囲について、相続人間で訴訟になっている場合。
- 申請義務を負う相続人自身が、重病などの理由で手続きを行えない場合。
- 申請義務を負う相続人が経済的に困窮し、登記費用を負担する能力がない場合。
単に「仕事が忙しかった」「法律を知らなかった」といった理由では、正当な理由として認められる可能性は低いと考えられます。
義務履行を円滑にするための新制度―「相続人申告登記」
3年以内に遺産分割協議がまとまらない、相続人が多すぎてすぐに登記申請の準備ができない――。
こうした困難な状況に対応するため、義務化と同時に合理的かつ簡易な負担軽減策として「相続人申告登記」制度が創設されました(不動産登記法第76条の3)。
制度の概要と法的効果
これは、相続人が法務局に対し、
「私が、この不動産の登記名義人の相続人の一人です」
と申し出るだけの非常にシンプルな手続きです。
この制度の最大のポイントは、この申出を行うことで、前述した不動産登記法第76条の2第1項の申請義務を履行したものとみなされるという法的効果です。
つまり、この申出さえしておけば、3年の期限を過ぎても過料を科される心配がなくなるのです。
手続きの簡便さ
- 相続人単独で可能:他の相続人の同意や協力は不要で、相続人の一人が単独で申し出ることができます。
- 添付書類が少ない:申出をする本人が、亡くなった登記名義人の相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出するだけで足ります。
遺産分割協議書や印鑑証明書などは一切不要です。 - 登録免許税が不要:相続登記で必要となる登録免許税がかかりません。
相続人申告登記の限界と注意点
この制度は非常に有用ですが、あくまでも「応急措置」である点を理解しておく必要があります。
- 権利関係は確定しない:この申出によって登記されるのは、申出人の氏名・住所等のみです。誰がどのくらいの割合(持分)で不動産を相続したのかは公示されません。
- 不動産の処分はできない:権利関係が確定していないため、この申出をしただけでは、その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることはできません。
最終的に不動産を処分・活用するためには、遺産分割協議を成立させ、その内容に基づいた正式な相続登記(所有権移転登記)を申請する必要があります。
この登記は、遺産分割が成立した日から3年以内に行う義務が別途課せられています。
未来への責任として、今こそ行動を
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題という、次世代に負の遺産を残しかねない社会課題に対応するための、避けては通れない法改正です。
改正法は、私たち国民に新たな「義務」を課す一方で、「相続人申告登記」という合理的な負担軽減策も用意しています。
これは、国民の事情に配慮しつつ、社会全体の利益を守ろうとする国の姿勢の表れと言えるでしょう。
相続は、誰にでも起こりうることです。法律の趣旨を正しく理解し、ご自身の状況に応じて、
- 3年以内に正式な相続登記を完了させる
- 期限内の登記が難しい場合は、ひとまず「相続人申告登記」を活用する
といった適切な対応を選択することが、これまで以上に強く求められています。
手続きが複雑で分からない、何から手をつけて良いか迷うという場合は、決して一人で抱え込まず、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。早期の対応こそが、将来の無用なトラブルや不利益を避け、あなたとご家族の大切な資産を確実に守るための最善の一手となるはずです。
株式会社Go不動産では相続登記の必要な土地、建物の売却相談も随時承っております。
お気軽にご連絡ください。
古家・空き家などの物件売却は
「Go(ゴー)不動産にお任せください」