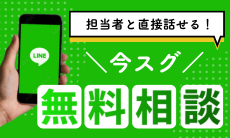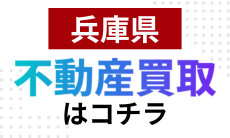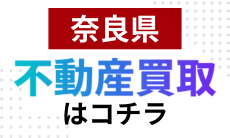相続の寄与分
【相続の寄与分】
親の介護や事業を手伝ったら「寄与分」で相続額が増える?寄与分制度
「長年、親の介護を一人で担ってきた」
「実家の農業を無給で手伝い、ずっと支えてきた」
親が亡くなったとき、こうした長年の貢献が全く考慮されず、他の兄弟姉妹と全く同じ相続分となると、どこか納得できない気持ちになるかもしれません。
実は、民法にはそうした特別な貢献(寄与)を相続において正当に評価するための「寄与分(きよぶん)」という制度が存在します。この制度を正しく理解し、活用することで、あなたの貢献に見合った財産を受け取れる可能性があります。
今回は、この「寄与分」という制度について、基本的な知識や計算方法、手続きの進め方までの解説していきます。
そもそも「寄与分」とは?
寄与分とは、一言でいえば「被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて法定相続分に上乗せして財産を受け取れる制度」のことです。
この制度の目的は、共同相続人間の実質的な公平を保つことにあります。
例えば、被相続人の財産形成に大きく貢献した相続人と、全く貢献していない相続人が同じ相続分を受け取るのは不公平だ、という考え方が根底にあります。
寄与分を主張できるのは、原則として「共同相続人」に限られます。
例えば、亡くなった方の長男の妻(お嫁さん)が熱心に介護をしていたとしても、その方は相続人ではないため、寄与分を主張することはできませんでした。
(※ただし、2019年の民法改正で、相続人以外の親族も「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりました。これについては後述します。)
「寄与分」が認められるための3つの条件
「少し手伝った」という程度では、残念ながら寄与分は認められません。
寄与分が法的に認められるには、以下の3つの重要な条件をすべて満たす必要があります。
- 相続人自身の行為であること 寄与行為は、相続人自身の行為でなければなりません。
- 「特別な」寄与であること これが最も重要なポイントです。夫婦間の協力義務や、親子・兄弟間の一般的な扶養義務の範囲を超えるような、無償またはそれに近い貢献である必要があります。
例えば、子が親の面倒を見るのはある程度当然と考えられているため、「時々実家に帰って様子を見ていた」程度では特別な寄与とは認められにくいでしょう。 - 財産の維持または増加との因果関係があること その貢献によって、「被相続人の財産が減るのを防いだ(維持)」または「財産を増やすことに繋がった(増加)」という明確な因果関係が必要です。
例えば、介護をしたことで高額な介護施設への入所を避けられ、結果として被相続人の財産が維持された、といった関係性が求められます。
寄与分が認められる5つの具体例(類型)
どのような行為が「特別な寄与」に当たるのでしょうか。
実務上、寄与分は主に以下の5つの類型に分類されます。
- ① 家業従事型 被相続人が営んでいた農業や商店などの事業を、無給または市場の相場より著しく低い給与で長期間手伝い、その事業の維持・発展に貢献した場合です。
- ② 金銭等出資型 被相続人に事業資金を援助したり、不動産の購入資金を提供したり、借金を肩代わりしたりして、財産の維持・増加に直接的に貢献した場合です。
- ③ 療養看護型 近年、最も主張されることが多い類型です。
病気や高齢の被相続人を、職業の看護師ではない相続人が無償で介護した場合です。
つきっきりの介護のために仕事を辞めざるを得なかった、などのケースが典型例です。 - ④ 扶養型 被相続人に特別な経済的援助が必要な状況で、本来被相続人が自分で支払うべき生活費を負担した場合です。
ただし、単に同居して面倒を見ていたというだけでは認められにくく、被相続人が要扶養状態にあったことが前提となります。 - ⑤ 財産管理型 被相続人が所有する賃貸アパートの管理や家賃の取り立て、固定資産税の支払いや不動産の修繕などを無償で行い、財産の価値を維持した場合です。
寄与分はいくら貰える?金額の計算方法
寄与分の金額は「この行為をしたら〇〇円」と法律で決まっているわけではなく、ケースバイケースで判断されます。
基本的には、「もしその貢献を専門家に依頼していたらいくらかかったか」を基準に計算されます。
下記は最も一般的な「療養看護型」の計算方法の考え方です。
【療養看護型の計算式】 介護報酬相当額(日当)×介護日数×裁量割合
- 介護報酬相当額(日当): 介護保険制度における要介護度などを参考にしますが、裁判例では1日あたり3,000円~8,000円程度で話し合われることが多くなっています。
- 介護日数: 実際に介護を行った日数です。
- 裁量割合: 親族間の協力義務などを考慮して、算出された金額から一定割合を差し引くためのものです。一般的には0.5~0.9程度の範囲で判断されます。
例えば、日当5,000円で3年間(1,095日)、つきっきりで介護し、裁量割合が0.7とされた場合、寄与分は約383万円(5,000円 × 1,095日 × 0.7)と評価される可能性があります。
寄与分を主張するための手続きと必要な証拠
寄与分を認めてもらうには、以下のステップで進めるのが一般的です。
- 遺産分割協議: まずは相続人全員での話し合いの場で、自身の寄与を主張し、全員の合意を目指します。
- 遺産分割調停: 話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合います。
- 遺産分割審判: 調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続きに移行し、最終的に裁判官が寄与分の有無や金額を判断します。
どの段階においても、主張を裏付ける客観的な証拠が何よりも重要になります。
口頭で「私が介護した」と主張するだけでは、他の相続人に納得してもらったり、裁判所に認めてもらったりするのは困難です。
【証拠の具体例】
- 療養看護型: 介護日記、要介護認定通知書、医師の診断書、介護サービスの領収書(一部利用をしている場合など)
- 家業従事型: タイムカード、業務日誌、帳簿、同業者の給与水準がわかる資料
- 金銭等出資型: 銀行の振込明細、通帳の記録、贈与契約書、借金の返済記録
- 共通する証拠: 被相続人の日記や手紙、メールやLINEのやり取り、他の親族や近隣住民の証言など
【参考】相続人以外は「特別寄与料」を請求できる
2019年7月1日の民法改正により、これまで寄与分を主張できなかった「相続人以外の親族」(例:長男の嫁)も、無償で介護などを行った場合、相続人に対して金銭を請求できる「特別寄与料」という制度が創設されました。
寄与分が遺産分割協議の中で決まるのに対し、特別寄与料は相続人に対して「私の貢献分を支払ってください」と金銭を請求する権利である点が大きな違いです。
請求できる期間が短い(相続開始を知ってから6ヶ月以内など)ため、注意が必要です。
【具体例でわかる】寄与分がある場合の相続分の計算
最後に、寄与分が認められた場合に、実際の相続分がどう変わるのかを見てみましょう。
【設例】
- 相続財産:5,000万円
- 相続人:長男、次男の2人
- 長男の介護の貢献が認められ、寄与分が1,000万円と確定した。
【計算ステップ】
- 「みなし相続財産」を計算する まず、相続財産全体から寄与分を差し引きます。
これを「みなし相続財産」と呼びます。
5,000万円(相続財産)−1,000万円(長男の寄与分)=4,000万円 - みなし相続財産を法定相続分で分ける 次に、みなし相続財産を各相続人の法定相続分で分けます。
4,000万円÷2人=2,000万円 これが、今回の相続における一人あたりの基本的な取り分となります。 - 各人の具体的な相続分を確定する
- 長男: 2,000万円(基本の取り分)+1,000万円(寄与分)=3,000万円
- 次男: 2,000万円
このように、長男の寄与分が認められたことで、具体的相続分に1,000万円の差が生まれることになります。
まとめ
寄与分は、あなたの長年の貢献が金銭的に報われる可能性のある重要な制度です。
しかし、その主張が認められるには「特別な寄与」であることと、それを裏付ける「客観的な証拠」が不可欠です。
もし「自分にも当てはまるかも?」と感じたら、まずはどんな貢献をしたか、それを証明できる資料は何かを整理することから始めてみてください。そして、相続が発生した際には、他の相続人に対して誠意をもって説明することが大切です。
当事者間での話し合いが難しい場合や、法的にきちんと主張したい場合は、相続問題に詳しい弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
Go不動産(ゴーフドウサン)では、今後利用する予定のない不動産の買取りを行なっております。
一戸建て・長屋・区分所有マンションの一室・倉庫・工場・一棟建物・連棟建て住宅・平屋・借地権付き建物・空地・駐車場・テナントビル・事業用店舗・店舗付き住宅など様々な物件を募集しております。
大阪市24区(北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区)/堺市7区(北区・東区・堺区・南区・中区・美原区・西区)/吹田市/高槻市/島本町/箕面市/池田市/豊中市/茨木市/摂津市/守口市/寝屋川市/門真市/枚方市/交野市/四條畷市/大東市/東大阪市/八尾市/松原市/忠岡町/高石市/和泉市/泉大津市/羽曳野市/柏原市/藤井寺市/岸和田市/貝塚市/泉佐野市/泉南市/阪南市/富田林市/大阪狭山市/河内長野市/岬町など
神戸市内全域/尼崎市/西宮市/芦屋市/伊丹市/宝塚市/川西市/三田市/明石市など
生駒市/奈良市/香芝市/大和郡山市/大和高田市/天理市/橿原市/平群町/斑鳩町など
上記以外の地域もご相談いただけますので、お気軽にご連絡下さい