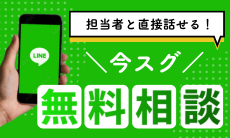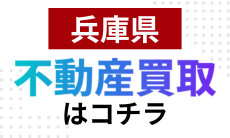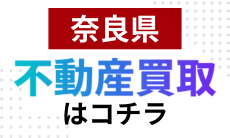法定後見制度:後見、保佐、補助
法定後見制度
日本の法定後見制度は、認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など、精神上の障害により判断能力が不十分な方々が安心して生活できるよう支援することを目的としています。
この制度は、本人の意思や権利を尊重しつつ、適切な援助や財産管理を行うことを主眼としており、2000年に施行されました。
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が設けられており、それぞれの状況に合わせたきめ細やかな支援が提供されます 1。
後見:判断能力を欠く常況
後見の対象となるのは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方です。
これは、自己の財産を管理・処分できないほど判断能力が欠けている状態を指し、支援を受けても契約などの意味や内容を自ら理解し、判断することができないレベルにまで判断能力が低下した場合が該当します。
重度の認知症患者や重度の知的障害者、精神障害者などがこの類型に該当します。
後見人には、日常生活に関する行為を除く、原則としてすべての法律行為に関する包括的な代理権と取消権が与えられます。
一方で、本人がほとんど判断能力を持たないため、後見人には同意権は与えられていません。
後見開始の審判を受けた本人は「行為能力を欠く常況」とみなされ、後見人の同意なしに行った行為は取り消される可能性があります。
保佐:判断能力が著しく不十分
保佐の対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である方です。
日常的な買い物程度は1人でできるものの、不動産の売買や金銭の貸し借りといった重要な財産行為を単独で行うことが難しい状態を指します。
裁判所の運用では、「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない」と認められる場合に保佐の要件に該当すると判断されます。
中程度の認知症患者などがこの類型に該当します。
保佐人には、民法第13条1項に定められた特定の重要な法律行為(例:借財、不動産の売買、訴訟行為など)について同意権が与えられ、本人が同意なく行ったこれらの行為は取り消すことができます。
また、特定の法律行為について必要に応じて家庭裁判所が個別に代理権を付与することも可能です。
本人は、これらの特定の行為については保佐人の同意が必要となりますが、それ以外の行為は単独で有効に行うことができます。
補助:判断能力が不十分
補助の対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である方で、法定後見制度の中で最も軽度の判断能力低下に対応します。
重要な財産行為について、自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があり、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の判断能力の者を指します。
軽度の認知症で物忘れが始まったばかりの方や、判断能力に不安があるがまだ自分で契約行為もできる場合がある方などがこの類型に該当します。
補助人には、家庭裁判所が指定した特定の法律行為に関する同意権と、同意なしに行われた行為を取り消す権限が与えられます。
また、特定の法律行為について個別に代理権を付与することも可能です。
これらの権限を補助人に付与する審判には、本人の同意が必要とされます。
本人は、家庭裁判所が指定した特定の行為についてのみ補助人の同意が必要となり、それ以外の行為は単独で有効に行うことができます。
まとめ
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という段階的な支援を提供することで、その意思と権利を最大限に尊重し、安心して生活できる社会の実現を目指しています。
この制度は、本人の保護と同時に、取引の相手方の法的安定性も考慮した、多面的な法的枠組みと言えるでしょう。
成年被後見人、保佐人及び補助人の所有する不動産の売却の際も「Go不動産(ごーふどうさん)」にお任せ下さい!