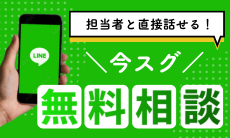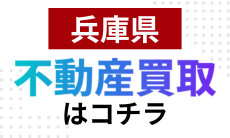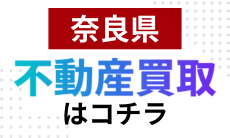瑕疵担保責任と契約不適合責任
不動産売買の「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違い
不動産という高額な資産の取引において、購入後に欠陥が見つかった場合の責任の所在は、買主・売主双方にとって極めて重要な問題です。
2020年4月1日の民法改正により、この責任に関するルールが従来の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」から「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」へと大きく変わりました。
本記事では、この二つの責任の違いを、定義、買主の権利、権利行使期間、実務への影響といった多角的な視点から解説します。
責任の前提:「隠れた瑕疵」から「契約の不適合」へ
まず、責任が発生する根本的な考え方が異なります。
瑕疵担保責任(旧法)の定義と範囲
瑕疵担保責任は、売買の対象となった不動産に「隠れた瑕疵」があった場合に、売主が負う責任でした。
ここでのポイントは「隠れた」という点で、これは「買主が取引時に通常の注意を払っても発見できなかった欠陥」を意味します。
買主が欠陥を知っていたり、少し注意すれば気づけたはず(善意無過失でない)の場合は、売主の責任を問えませんでした。
瑕疵には、以下のような種類があります。
- 物理的瑕疵: 雨漏り、シロアリ被害、建物の構造上の欠陥、土地の土壌汚染など。
- 法律的瑕疵: 建築基準法に違反しており再建築ができない、接道義務を果たしていない土地など、法律上の制限により目的の利用ができない状態。
- 心理的瑕疵: 過去に自殺や殺人事件があった(いわゆる事故物件)、近隣に暴力団事務所があるなど、住み心地に影響を与える心理的な抵抗を感じる事由。
- 環境的瑕疵: 近隣にゴミ焼却場や騒音・悪臭を発生させる施設があるなど、周辺環境に問題がある状態。
この責任は、法律が公平の見地から特別に売主に課した「法定責任」と解釈されていました。
契約不適合責任(現行法)の定義と範囲
一方、契約不適合責任は、引き渡された不動産が「種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない」場合に、売主が負う責任です。
ポイントは、「隠れているか」どうかは問われず、契約書や重要事項説明書に記載された内容と、実際の不動産の状態が一致しているかが基準となる点です。
例えば、「雨漏りはない」と契約書に記載されていれば、引き渡し後に雨漏りが発覚した場合、それが買主にとって容易に発見できるものであったとしても、契約不適合責任を追及できます。
この変更により、売主と買主が契約時にどのような内容で合意したかが、これまで以上に重要になりました。
この責任は、契約内容をきちんと実現するという「債務不履行責任」の一種として位置づけられています。
買主の権利:選択肢の拡大で手厚い保護へ
買主が請求できる権利の内容も、契約不適合責任になって大きく拡充されました。
瑕疵担保責任で認められた買主の権利
旧法下では、買主の選択肢は以下の2つに限られていました。
- 損害賠償請求: 瑕疵によって生じた損害(調査費用や修補費用など)の賠償を求める権利。
- 契約解除: 瑕疵の程度が重大で、契約の目的(例:居住)を達成できない場合に限り、契約そのものを白紙に戻すことができました。
契約不適合責任で認められる買主の権利
現行法では、上記に加えて新たに2つの権利が追加され、買主は状況に応じて最適な手段を選べるようになりました。
- 追完請求権(まずこれを請求するのが原則):
- 修補請求: 雨漏りや設備の故障など、欠陥部分の修理を求める権利。
- 代替物の引渡し請求:(不動産では稀ですが)代替物を引き渡すよう求める権利。
- 不足分の引渡し請求: 土地の面積が契約より少なかった場合に、不足分を引き渡すよう求める権利。
- 代金減額請求権: 追完請求をしても売主が応じない場合や、修補が不可能な場合に、不適合の度合いに応じて売買代金の減額を求める権利。
- 損害賠償請求: 追完請求や代金減額請求とあわせて請求可能。賠償される範囲も、契約が有効と信じたことによる損害(信頼利益)だけでなく、契約が完全に履行されていれば得られたはずの利益(履行利益、例:転売益)まで対象が広がり、買主保護が強化されました。
- 契約解除: 追完を催告しても応じない場合や、契約の目的を達成できない場合に認められます。
このように、まずは「契約通りの状態にしてください(追完請求)」と求め、それが叶わない場合に次の手段(代金減額など)へ進むという、段階的で合理的な解決プロセスが用意されたのが大きな特徴です。
売主の責任:無過失責任から債務不履行責任へ
売主が責任を負うための条件も変化しました。
- 瑕疵担保責任: 無過失責任であり、売主自身に過失(落ち度)がなくても、隠れた瑕疵があれば責任を負わなければなりませんでした。
- 契約不適合責任: 債務不履行責任の一種です。これにより、損害賠償請求については、売主に帰責事由(故意・過失)がなければ責任を負わないことになりました。
ただし、追完請求や代金減額請求、契約解除については、原則として売主に帰責事由がなくても応じる必要があります。 この点は注意が必要です。
権利行使期間:知ってから1年以内の「通知」でOKに
権利を行使できる期間のルールも、買主にとって有利に変更されました。
- 瑕疵担保責任: 買主は、瑕疵の存在を知った時から1年以内に、損害賠償請求や契約解除といった権利を「行使」する必要がありました。
裁判を起こすなど、具体的なアクションまで求められるため、買主の負担は大きいものでした。 - 契約不適合責任: 買主は、契約との不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に「通知」すればよいとされました。
内容証明郵便などで「契約内容と違う箇所がある」と知らせるだけで権利が保全され、その後の具体的な請求(追完請求など)は、別途定められた消滅時効(知った時から5年、または引き渡しから10年)にかからない限り、通知後に行うことが可能です。
これにより、買主は落ち着いて交渉や準備を進められるようになりました。
実務への影響:契約書とインスペクションの重要性
この法改正は、実際の不動産取引に大きな影響を与えています。
契約書・重要事項説明書の記載
「契約内容」が全ての基準となるため、契約書や重要事項説明書の記載が以前にも増して重要になりました。
売主としては、物件の状態(例えば、古い設備の現状や過去の修繕履歴など)をできる限り正確に記載し、「この状態のまま引き渡す」という合意を明確にすることで、将来のトラブルを避けることができます。
免責特約の扱い
契約不適合責任は、当事者間の合意(特約)によって、その内容を変更したり、責任を免除したりすることが可能です。中古住宅の個人間売買では、「売主は契約不適合責任を一切負わない」とする免責特約が結ばれることも少なくありません。
ただし、売主が宅地建物取引業者である場合は、宅建業法第40条により、買主保護のために引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定より買主に不利となる特約は無効とされます。
ホームインスペクション(住宅診断)の普及
物件の状態を専門家の目で客観的に評価するホームインスペクションの重要性が高まっています。
売主はインスペクションを行うことで物件の状態を正確に把握し、契約書に明記できます。
買主もインスペクションの結果を基に納得して契約することで、後の「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。
民法改正による「契約不適合責任」への移行は、単なる名称変更ではなく、不動産取引における当事者の権利義務関係を根本から見直すものです。
契約書という「約束事」を基点とすることで、より明確で合理的なルールとなり、買主の保護が手厚くなったと言えるでしょう。
不動産を売買する際は、この違いを正しく理解し、専門家とも相談しながら、慎重に契約を進めることが不可欠です。
大阪・兵庫・奈良など関西エリアの不動産の売却サポートは「Go不動産」にお任せ下さい!
ご相談のお電話をいただければ、当日のその日に「無料」で出張価格査定も可能です!
戸建て・マンション・土地・店舗など不動産の種類は問いません!
いつでもお電話お待ちしております!
株式会社Go不動産
TEL:06-6155-4564 / FAX:06-6155-4566
MAIL:info@go-fudosan.com