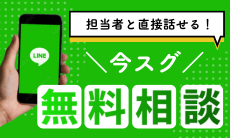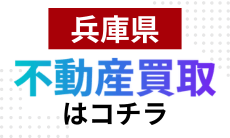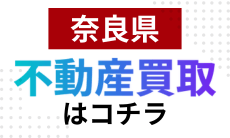【借地権】建物買取請求権とは?
建物買取請求権

※画像はイメージ写真です
「親から相続した実家は借地だった」
「購入を検討している魅力的な中古戸建てが、借地権付きだった」
昭和の時代、日本の都市部でマイホームを持つ際、土地を借りて家を建てる「借地権」はごく一般的な選択肢でした。
時代は流れ、現在では新しく戸建てを建てるために普通借地権契約を結ぶケースは以前より少なくなりました。
しかし、当時結ばれた何十年にもわたる借地契約は今なお日本中に数多く存在し、相続や建物の売買といったタイミングで、多くの方がこの複雑な権利に直面しています。
また、近年では定期借地権付きのマンションが供給されるなど、「土地を借りて建物を所有する」という形は、現代においても決して他人事ではありません。
そして、この借地契約にいつか訪れる「終了」の局面。
「契約の更新時期が近づいてきたが、地主が更新してくれないと言っている…」
「長年住んだこの家、取り壊して更地で返すしかないのだろうか?」
「地主として、契約が終わったら本当に土地は返ってくるのだろうか?」
こうした切実な問題に対する法的な解決策が想定されており、それが「建物買取請求権」です。
この権利は、一定の要件を満たせば、借地人が地主に対して「この建物を時価で買い取ってください」と一方的に請求できる、非常に強力なものです。

この記事では、「建物買取請求権」について、以下の点を解説します。
- 制度の趣旨: なぜこのような強力な権利が認められているのか?
- 行使の要件: どんな場合にこの権利を使えるのか?
- 実務上の指針: 借地人・地主がそれぞれ何をすべきか?
借地権付き建物の所有者及び底地の所有者のどちらの立場でも知っておく必要がある基本的知識です。
第1章:建物買取請求権とは?~借地人と社会を守る制度の趣旨
まず、建物買取請求権がどのような権利なのか、その核心と背景にある考え方を理解しましょう。

権利の核心と法的根拠
建物買取請求権とは、借地契約が終了する際に、借地人が所有する建物を地主に対し、適正な価格(時価)で買い取ることを請求できる権利です。
この権利の主な法的根拠は、借地借家法の2つの条文です。
- 借地権の存続期間満了の場合(借地借家法第13条): 契約期間が満了し、契約が更新されなかったときに、借地人が行使します。
- 借地権の譲渡・転貸が承諾されない場合(借地借家法第14条): 借地人が建物を第三者に売却(=借地権の譲渡)しようとしたが、地主がそれを承諾しなかったときに、その建物を取得した第三者が行使します。
なぜ存在する?2つの重要な制度趣旨
なぜ法律は、地主の意思に関わらず建物を買い取らせるという、これほど強力な権利を借地人に与えたのでしょうか。その背景には、2つの重要な目的があります。
- 借地人の投下資本の回収
建物を建てるには、当然ながら多額の費用がかかります。
もし借地契約が終了するたびに、まだ十分に使える建物を自費で取り壊し、更地にして返還しなければならないとしたら、借地人は安心して建物を建てられません。
そこで、建物という形で投じた資本を、時価で回収する機会を保障することで、借地人の利益を守っているのです。 - 社会経済的損失の防止
まだ価値のある建物を取り壊すことは、所有者個人の損失であるだけでなく、社会全体にとっても大きな損失です。
資源の無駄遣いを防ぎ、既存の建物を有効活用することは、社会経済的に見て合理的です。
建物買取請求権は、この観点からも建物の存続を促す役割を担っています。
「形成権」かつ「強行規定」という強力な性質
この権利が「強力」と言われる理由は、その法的な性質にあります。
- 形成権
建物買取請求権は「形成権」に分類されます。
これは、借地人が「買い取ってほしい」という一方的な意思表示をすれば、地主の承諾がなくても、その時点で建物に関する売買契約が成立することを意味します。
地主は「買いたくない」と拒否することはできません。 - 強行規定
この権利に関する借地借家法の規定は「強行規定」です。
これは、当事者間の特約で、この権利をあらかじめ排除することができないことを意味します(借地借家法第16条)。
例えば、借地契約書に「契約終了時、借地人は建物買取請求権を一切行使しない」という条項があっても、その条項は法律上、無効となります。
このように、建物買取請求権は、借地人を手厚く保護するために法律が用意した、非常に重要なセーフティネットなのです。
第2章:権利行使のハードル~認められるための3つの必須要件
強力な権利である一方、誰でも無条件に行使できるわけではありません。
法律は、権利を行使するための厳格な要件を定めています。
ここでは、最も一般的な「期間満了で更新されない場合(借地借家法13条)」を例に、3つの必須要件を見ていきましょう。

要件1:借地契約の期間が満了し、更新されないこと
まず大前提として、借地契約が正規に期間満了を迎える必要があります。
そして、その後「契約が更新されない」ことが確定しなければなりません。
具体的には、以下のような状況です。
- 地主が「正当な事由」をもって更新を拒絶した場合
地主が、自ら土地を使用する必要があるなど、法律上認められる「正当な事由」を主張し、契約更新を拒絶した場合です。
【注意点】合意解約の場合は原則として行使できない
当事者双方が話し合い、「お互い合意の上で契約を終わりにしましょう」という合意解約の場合、通常は建物買取請求権を放棄することが合意の内容に含まれていると解釈されるため、原則としてこの権利は行使できません。
※借地人が契約の更新請求をしなかった場合は?
この場合は非常に判断が難しいところです。
一般的な会話を想定するのならば、土地の借主側から「これ以上契約を更新しません」と地主側に言ったとすると、地主側は「では、土地賃貸借契約を解除しましょう」となることが多いでしょう。
つまりこの場合には、【お互いが合意して解除した】と捉えることもできるため、建物買取請求はできない可能性があります。
要件2:借地上に借地人所有の建物が存在すること
当然ですが、買い取ってもらうべき「建物」が、契約終了時に土地上に存在している必要があります。
火災などで建物が滅失してしまっていれば、請求することはできません。
また、その建物は借地人の所有物でなければなりません。
建物の登記が借地人名義になっていれば所有権の証明は容易ですが、法律上は登記の有無は必須要件ではありません。
ただし、後々のトラブルを防ぐためにも、所有権登記はしておくべきです。
要件3:借地人に契約違反(債務不履行)がないこと
これが、実務上最も重要で、トラブルになりやすい要件です。
建物買取請求権は、あくまで「誠実に契約上の義務を果たしてきた借地人」を保護するための制度です。
したがって、借地人側に以下のような契約違反(債務不履行)があった結果、地主が信頼関係を破壊されたとして契約を解除した場合には、建物買取請求権は認められません。
- 地代(賃料)の滞納
- 地主に無断での大規模な増改築
- 契約で定められた用途に違反した建物の使用
- 地主に無断での借地権の譲渡や土地の転貸(又貸し)
これらの行為は、地主との信頼関係を根底から覆すものと評価されます。
その結果として契約を解除された借地人は、法律の保護を受ける資格がない、と判断されるのです。
第3章:時価はどう決まる?「場所的利益」という重要概念
買取請求権が認められたとして「いくらで買い取ってもらえるのか?」という価格の問題も起こります。
法律は「時価」で買い取ることを定めていますが、この「時価」がクセモノで、地主と借地人の間で争いになりやすい点です。

買取請求権における「時価」は、大きく以下の2つの要素で構成されると考えられています。
時価 = ① 建物自体の価格 + ② 場所的利益
① 建物自体の価格
これは比較的イメージしやすいでしょう。
その建物をもう一度新しく建てたらいくらかかるか(再調達原価)から、築年数に応じた価値の減少分(経年劣化・減価償却)を差し引いて計算されます。
② 場所的利益
これが非常に重要かつ、算定が難しい概念です。
「場所的利益」とは、その建物がその場所にあることによって生じる付加価値のことです。
例えば、同じ建物でも、都心の一等地にある場合と、郊外の不便な場所にある場合とでは、その価値は全く異なります。
駅に近い、商業施設が充実している、周辺環境が良いといった立地条件がもたらす事実上の利益を金銭的に評価したものが「場所的利益」です。
これは借地権の価格そのものではありませんが、借地権が存在することによる利益を考慮したものです。
実務上は、土地の更地価格の10%~30%程度を場所的利益として考慮することが多いですが、これはあくまで目安であり、個別具体的な事情によって大きく変動します。
この場所的利益の評価をめぐって当事者の意見が対立することが多く、最終的には不動産鑑定士による鑑定や、裁判所の判断によって決定されることになります。
第4章:実務上の示唆~借地権者と地主のための指針
最後に、これまでの解説を踏まえ、借地権者(借主)と借地権設定者(地主)が、円満な関係を築き、無用な紛争を避けるために、それぞれ心に留めておくべき指針をまとめます。

借地権者(借主)への指針
- 誠実な契約履行の徹底
何よりもまず、地代を契約通りに支払うこと。
滞納しないという意識が重要です。
これが、あなたの権利を守る最大の防御策です。 - 「報告・連絡・相談」の徹底
建物の増改築や、第三者への譲渡・転貸を少しでも考える場合は、必ず事前に地主に相談し、書面で承諾を得てください。
口約束はトラブルの元です。 - 記録の保管
契約書はもちろん、更新時の合意書、各種承諾書、地代を支払った記録(振込明細や領収書)など、契約に関する全ての書類を大切に保管しておきましょう。
いざという時にあなたを守る証拠となります。 - 専門家への早期相談
何かのアクションを起こす前に、早めに弁護士や不動産の専門家に相談し、交渉や買取請求の可能性についてアドバイスを受けましょう。
借地権設定者(地主)への指針
- 契約違反への迅速かつ適切な対応
借地人に地代の滞納などの契約違反があった場合、放置は禁物です。
内容証明郵便で催告するなど、証拠に残る形で迅速かつ適切に対応することが、あなたの権利を守ります。 - 更新拒絶には「正当事由」が必須
単に「土地を返してほしい」という理由だけで更新を拒絶することは、法律上非常に困難です。
自己使用の具体的な必要性や、十分な額の立退料の提供など、客観的に認められる「正当な事由」を準備する必要があります。 - 安易な合意解約のリスク
借地人との話し合いで契約を合意解約する場合、建物買取請求権をどう扱うか(放棄を明確にするのか、解決金として一定額を支払うのか等)を合意書に必ず明記してください。 - 専門家への早期相談
借地権者(借主)への指針と同じですが、早めに専門家に相談するなどして、今後の展開を予想し、対策を準備することが大切です。
まとめ
建物買取請求権は、長年にわたり土地を借り、その上に生活の基盤を築いてきた誠実な借地人を保護するための、非常に強力な権利です。
その権利が認められるか否かを分ける最大の分水嶺は、突き詰めれば「契約上の義務をきちんと果たし、地主との信頼関係を維持してきたか」という、ごく当たり前の点にあります。
地主と借地人は、ともすれば対立関係にあるように見られがちです。
しかし、双方が契約内容と法律の趣旨を正しく理解し、互いの立場を尊重しながら誠実な関係を築くことこそが、無用な紛争を避け、双方の財産と平穏な生活を守るための最善の道と言えるでしょう。

借地権のトラブル、専門家が解決します
「建物買取請求権の交渉がまとまらない」
「地主との関係がこじれてしまった」
「権利関係が複雑で、誰に相談すればいいか分からない」
借地権が絡む不動産の問題は、当事者だけでの解決が非常に困難です。
株式会社Go不動産は、このような複雑なご事情を抱えた不動産の買取や売却サポートを専門としています。
借地権付きの古い家、再建築不可物件、共有名義の土地など、どのような状態でもご相談ください。
司法書士など専門家と連携し、複雑な権利関係の整理から、地主様との交渉まで、お客様の立場でサポート。
片付け不要の家具・家電など、お部屋をそのままで、スピーディーな買取を実現できる【まるごと買取パック】プランもございます。
私たちは、不動産を通じてお客様の人生の節目に寄り添い、円満な解決と新たな一歩を応援することをお約束します。
ご相談・査定はすべて無料、秘密厳守で対応いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ】
株式会社Go不動産
大阪府知事(1)第65958号
TEL: 06-6155-4564(ご相談は年中無休)
LINE: @gofudosan(友だち追加で気軽に相談)
MAIL: info@go-fudosan.com
【主な対応エリア】 大阪府全域、兵庫県、奈良県
【買取強化エリア】 北摂地域(豊中市、吹田市、茨木市など)