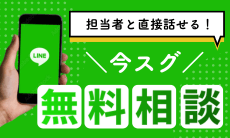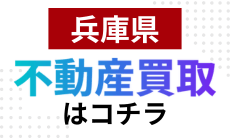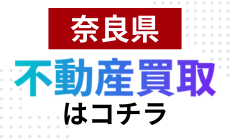遺産分割
遺産分割とは
遺産分割は、大切な家族を亡くした後、残された方々が直面する重要な手続きです。しかし、
「何から手を付けて良いのか分からない」
「トラブルになったらどうしよう」
といった不安を抱える方も少なくありません。
このブログでは、遺産分割に関する基本的な知識から、具体的な手続き、よくある問題と解決策まで、専門知識がない方にも分かりやすく解説します。
遺産分割とは?
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続する権利を持つ方々(相続人)で分け合う手続きのことです。
被相続人が亡くなると、その財産は一旦、相続人全員の共有財産となります。
この共有状態を解消し、それぞれの相続人のものとして確定させるのが遺産分割です。
民法では、遺産分割について以下の基本的なルールが定められています。
- 民法898条: 相続財産が共有となること。
- 民法906条: 遺産分割は、遺産の種類や性質、各相続人の状況(年齢、職業、心身の状態、生活状況など)を考慮して行うこと。
- 民法900条、901条: 法定相続分(法律で定められた相続の割合)。
- 民法902条1項: 遺言で相続分が指定されている場合は、そちらが優先されること。
遺産分割の種類
遺産分割には、大きく分けて以下の4つの方法があります。
- 遺言による分割: 被相続人が生前に遺言書を作成し、遺産の分け方を指定していた場合。原則として遺言が優先されます。
- 協議による分割: 相続人全員が話し合い、合意に基づいて遺産を分割する方法。最も一般的な方法です。
- 調停による分割: 協議でまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いを進める方法。
- 審判による分割: 調停でも合意に至らない場合、家庭裁判所の裁判官が遺産の分割方法を決定する方法。
遺産分割の対象となる財産、ならない財産
すべての財産が遺産分割の対象となるわけではありません。
対象となる財産
被相続人が所有していたほとんどの財産が対象となります。
- プラスの財産: 土地、建物などの不動産、預貯金、有価証券(株式など)、自動車、貴金属、骨董品など。
- マイナスの財産: 借金、未払金、ローンなど(これらは遺産分割とは別に、相続人が引き継ぐことになります)。
対象とならない財産
以下の財産は、原則として遺産分割の対象にはなりません。
- 祭祀財産(さいしざいさん): お墓、仏壇、位牌、家系図など。これらは相続財産には含まれず、祭祀を主宰すべき人が承継します。
- 生命保険金: 原則として、保険契約で指定された受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とはなりません。
- 死亡退職金: 原則として、会社の規定や契約で指定された受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とはなりません。
遺産分割の具体的な方法とメリット・デメリット
実際に遺産を分ける際には、いくつかの方法があります。
それぞれの特徴を知り、状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
1. 現物分割
遺産をそのままの形で各相続人に分ける方法です。
- 例: 長男には実家(不動産)、次男には預貯金、長女には株式といった具合に現物を分けます。
- メリット: 手続きが比較的シンプルで、売却などの手間がかからない。
愛着のある不動産などを残しやすい。 - デメリット: 財産の価値が均等になりにくく、不公平感が生じやすい。
不動産など物理的に分けにくい財産は分割が難しい。
2. 換価分割(かんかぶんかつ)
遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。
- 例: 実家を売却し、得られた売却益を相続分に応じて現金で分けます。
- メリット: 公平に分割しやすい。
- デメリット: 不動産の売却には手間や費用(仲介手数料、税金など)がかかる。
売却まで時間がかかることがある。
3. 代償分割(だいしょうぶんかつ)
特定の相続人が遺産を単独で取得し、その代償として他の相続人に現金などを支払う方法です。
- 例: 長男が実家を相続し、その代わりとして、実家に見合う代償金(例えば1000万円)を次男と長女に支払う。
- メリット: 愛着のある不動産などを残せる。
共有名義による将来のトラブルを避けられる。 - デメリット: 代償金を支払う相続人に経済的負担がかかる。
代償金の評価や金額を巡ってトラブルになることがある。
4. 共有分割
遺産を相続人全員の共有名義にする方法です。
- 例: 実家を長男と次男が2分の1ずつの割合で共有名義にする。
- メリット: 一時的に公平な形にできる。
- デメリット: 将来、売却や修繕が必要になった際に、共有者全員の合意が必要となるため、トラブルになりやすい。
固定資産税の支払いなども共同責任となる。
遺産分割で考慮すべき要素
遺産分割では、単に法定相続分通りに分けるだけでなく、個別の事情も考慮されることがあります。
特別受益(とくべつじゅえき)
特定の相続人が、被相続人から生前に多額の贈与を受けていたり、遺言によって特別な利益(遺贈)を得ていたりした場合、それを特別受益といいます。
この特別受益は、遺産分割の際に相続財産に持ち戻して(加算して)計算され、特別受益を受けた相続人の相続分が調整されます。
- 例: 長男が被相続人から生前に不動産の購入資金として1000万円の贈与を受けていた場合、遺産総額に1000万円を加えて計算し、長男の相続分から1000万円を差し引きます。
【民法改正による重要ポイント】
令和5年4月1日より施行された民法改正により、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益の持ち戻しを主張できなくなりました。 これは、遺産分割を早期に安定させるための改正です。
寄与分(きよぶん)
相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した方がいる場合、その貢献分を寄与分として考慮し、他の相続人よりも多くの財産を取得できる制度です。
- 例: 親の介護を長年にわたって無償で行い、介護費用を負担したことで、被相続人の財産が減るのを防いだ場合など。
【民法改正による重要ポイント】
特別受益と同様に、相続開始から10年を経過すると、原則として寄与分の主張ができなくなりました。
遺産分割協議がまとまらない場合の対処法とトラブル事例
相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまらないケースは少なくありません。
よくあるトラブル事例
- 感情的な対立: 相続人同士の長年の確執や感情的なしこりが原因で、話し合いが進まない。
- 特定の相続人による遺産の独占・隠蔽: 一部の相続人が財産を隠したり、勝手に使い込んだりする。
- 財産の評価に対する意見の相違: 不動産などの評価額について意見が対立する。
- 介護の貢献度を巡る争い: 介護をしていた相続人が寄与分を主張し、他の相続人と対立する。
- 遺留分(いりゅうぶん)侵害: 遺言書の内容が、特定の相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害している。
対処法
- 専門家への相談: まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
客観的なアドバイスや、法的な観点からのサポートが受けられます。弁護士は代理人として交渉にあたることもできます。 - 遺産分割調停: 相続人同士の話し合いが難しい場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停委員が間に入り、相続人それぞれの意見を聞きながら、合意形成を促してくれます。 - 遺産分割審判: 調停でも合意に至らない場合、自動的に遺産分割審判へ移行します。
審判では、裁判官が法的な判断に基づいて遺産分割の方法を決定します。
トラブルを避けるためには、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが最も有効です。
また、相続人全員で建設的な話し合いを心がけ、必要であれば早めに専門家を頼ることが大切です。
遺産分割手続きに必要な書類と情報
遺産分割の手続きには、様々な書類が必要になります。
事前に準備しておくことで、スムーズに進めることができます。
共通して必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類: 相続人を確定させるために必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本または抄本: 相続人であることを証明します。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票: 被相続人の最後の住所を証明します。
- 相続人全員の印鑑登録証明書: 遺産分割協議書に押印する印鑑が実印であることを証明します。
- 遺産分割協議書: 相続人全員の合意内容を記した重要な書類です。
- 財産目録: 被相続人のすべての財産(プラス・マイナス含む)を一覧にしたものです。
特定の財産の手続きに必要な書類
- 不動産の相続登記: 不動産の固定資産評価証明書、相続人の住民票など。
- 預貯金の払い戻し: 金融機関所定の書類、通帳、キャッシュカードなど。
- 有価証券の名義変更: 証券会社所定の書類など。
これらの書類は、取得に時間がかかるものもあるため、早めに準備に取り掛かることをお勧めします。
遺産分割に伴う相続税とその他の税金
遺産を相続した場合、相続税がかかる可能性があります。
相続税の基本的な考え方
- 基礎控除額: 相続税には基礎控除額が設けられています。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
- 相続財産の合計額がこの基礎控除額を超えた場合、相続税の申告・納税が必要になります。
- 申告・納付期限: 相続税の申告と納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが課されることがあります。
相続税を軽減する主な特例
- 配偶者の税額軽減: 配偶者が相続した財産については、1億6,000万円、または配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
- 小規模宅地等の特例: 被相続人が住んでいた宅地や事業を営んでいた宅地など、一定の要件を満たす場合には、その宅地の評価額を大幅に減額できます。
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠: 「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税がかかりません。
その他の税金
- 所得税・住民税: 相続した不動産を売却した場合など、利益が生じると譲渡所得税がかかることがあります。
- 固定資産税: 不動産を相続した場合、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
- 登録免許税: 不動産の相続登記を行う際に発生します。
- 不動産取得税: 相続による不動産の取得には原則として課税されませんが、遺贈など特定のケースでは課税されることがあります。
税金に関する手続きは複雑なため、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
遺産分割は、故人への感謝の気持ちを大切にしつつ、残された家族が新たな生活を送るための大切な区切りです。
このブログが、皆さんの遺産分割手続きの一助となれば幸いです。
遺産分割は、個々のケースで状況が大きく異なります。少しでも不安や疑問があれば、弁護士、司法書士、税理士といった専門家へ早めに相談し、適切なアドバイスを受けることが、トラブルを防ぎ、円滑な手続きを進めるための鍵となります。
Go不動産(ごーふどうさん)では、関西エリア(大阪府・兵庫県・奈良県・京都府・和歌山県)を中心に、様々な不動産の取り扱いを行なっております。
遺産分割「前」の土地・建物についてもご相談いただくことができますので、お気軽にご連絡下さい。