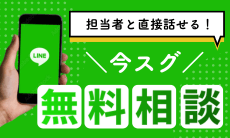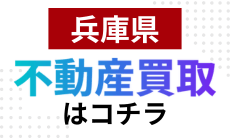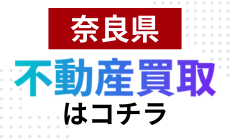共有持分の共有物分割について
共有持分の共有物分割について
不動産を複数人で所有する「共有」状態は、相続や共同購入などによって発生します。
しかし、共有状態は将来的なトラブルの原因となることも少なくありません。
特に、共有者間で意見の対立が生じた場合、共有状態を解消するための共有物分割が重要になります。
この記事では、共有持分の共有物分割について、その基本的な概念から具体的な分割方法、手続き、費用、税金、そして実務上の留意点まで、詳しく解説していきます。
共有持分と共有物分割の基本
共有とは?共有持分とは?
共有とは、一つの物を複数の人が共同で所有している状態を指します。
例えば、兄弟で実家を相続した場合や、夫婦でマンションを購入した場合などがこれに当たります。
それぞれの共有者がその物に対して持つ権利の割合を共有持分と言います。持分は通常、金銭を出した割合や、遺産分割協議で合意した割合に応じて決まります。
共有物分割とは?
共有物分割とは、共有状態にある不動産を、各共有者が単独で所有する状態に解消する手続きです。
これにより、共有者間の権利関係が明確になり、将来的なトラブルを避けることができます。
民法第256条第1項は、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と定めており、共有者には共有物分割請求権が認められています。
これは、共有状態が私有財産権の行使を妨げ、円滑な経済活動を阻害する可能性があるため、その解消を促す趣旨があります。
共有物分割の具体的な方法
共有物分割には、主に以下の3つの方法があります。
1. 現物分割
現物分割は、共有物を物理的に分割し、各共有者がその一部を単独所有する方法です。例えば、広い土地を複数に分筆して、それぞれの共有者がその土地を単独で取得するケースがこれに当たります。
- メリット
各共有者が現物をそのまま所有できるため、利用状況によっては最も望ましい形となります。
原則として贈与税や譲渡所得税が課税されないため、税負担が少ないのが特徴です。 - デメリット
共有物の性質上、物理的な分割が困難な場合や、分割によって価値が著しく減少する場合があります。
特に建物などの場合は分割が難しくなります。また、分筆登記などの費用がかかります。 - 留意点
分割後の各土地が建築基準法上の接道義務を満たすか、利用価値が維持されるかなどを考慮する必要があります。
持分割合と異なる割合で分割した場合、その差額に対して贈与税や譲渡所得税が課税される可能性があるので注意が必要です。
2. 代償分割(全面的価格賠償)
代償分割は、共有者の一人が共有物全体を単独で取得し、その代わりに他の共有者に対して、持分に応じた金銭を支払う方法です。
民法改正により明文化された全面的価格賠償がこれに該当します。
- メリット
共有物を物理的に分割する必要がないため、不動産の価値を維持しやすいです。
特に、居住用不動産や一体として利用価値が高い不動産に適しています。 - デメリット
共有物全体を取得する共有者に、他の共有者への支払い能力が必要です。
また、金銭を受け取る側には譲渡所得税が課税される可能性があります。 - 留意点
支払う代償金の金額は、共有物の適正な評価に基づいて決定されるべきです。
裁判所も公平な価格賠償の実現を重視します。
3. 換価分割(代金分割)
換価分割は、共有物全体を売却し、その売却代金を各共有者が持分割合に応じて分配する方法です。
- メリット
最もシンプルで公平な分割方法と言えます。
共有物を分割できない場合や、共有者間に代償金を支払う能力がない場合に有効です。 - デメリット
共有物を売却する必要があるため、思い入れのある不動産を手放すことになる点が挙げられます。
また、売却にかかる費用や、売却益に対して各共有者に譲渡所得税が課税されます。 - 留意点
売却価格が共有者全員の合意を得られるかが重要です。
不動産市場の状況によっては、希望する価格で売却できないリスクもあります。
共有物分割の手続き
共有物分割は、まず共有者間の協議から始まります。
協議がまとまらない場合は、裁判所の手続きに移行することになります。
1. 協議による分割
最も望ましいのは、共有者全員が話し合い、合意に基づいて分割する方法です。
- 手順
共有者全員で分割方法(現物分割、代償分割、換価分割)や、具体的な条件(代償金の額、分筆方法、費用の負担割合など)について話し合います。 - 共有物分割協議書
合意した内容は、後々のトラブルを防ぐためにも、必ず共有物分割協議書として書面に残し、共有者全員が署名捺印(実印)します。
この協議書は、所有権移転登記などの手続きに必要となります。
2. 裁判による分割
協議がまとまらない場合や、共有者の中に話し合いに応じない人がいる場合は、裁判所の手続きに移行します。
- 調停
まずは家庭裁判所に共有物分割調停を申し立てます。
調停委員を介して話し合いを進め、合意形成を目指します。
調停で合意できれば、調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます。 - 訴訟
調停でも合意に至らなかった場合、地方裁判所に共有物分割訴訟を提起します。
裁判所が共有物の性質や利用状況、共有者の希望などを総合的に考慮し、最も適切な分割方法を判決で命じます。
裁判所が考慮する要素と判断基準
裁判所は、現物分割を原則としつつ、それが困難な場合は代償分割(全面的価格賠償)や換価分割を検討します。
判決では、以下のような要素が考慮されます。
- 共有物の形状、面積、位置、利用状況
現物分割が可能か、分割後の利用価値が維持されるかなどを判断します。 - 共有に至った経緯
相続、共同購入、贈与など、共有状態になった経緯も考慮されることがあります。 - 各共有者の意向、利用状況、経済状況
各共有者が共有物に対して抱く思いや、実際に利用しているか、代償金を支払う能力があるか、受け取ることで生活に支障がないかなどが考慮されます。 - 不動産鑑定士による評価
共有物の適正な価格を把握するため、不動産鑑定士による評価が非常に重要視されます。
これにより、客観的で公平な分割が期待できます。
共有物分割に伴う費用、その他の留意事項
共有物分割には、様々な費用が発生します。
また、実務上注意すべき点も多々あります。
費用 ※一例のため、詳しく知りたい方は各専門家にご相談ください
| 費用の種類 | 概算 | 負担者(一般的なケース) |
| 弁護士費用 | 着手金(20~50万円)、報酬金(経済的利益の〇%) | 依頼した共有者。ただし、訴訟費用として最終的に敗訴者が負担する場合も。 |
| 訴訟費用 | 数万円~数十万円(印紙代、予納郵券代など) | 原則として折半、または勝訴者が相手に請求。 |
| 不動産鑑定費用 | 30~80万円(不動産の種類、規模による) | 協議の場合は折半、訴訟の場合は原則として裁判所が指定した共有者が予納。 |
| 測量費用(境界確定) | 30~100万円(土地の状況による) | 現物分割の場合、原則として折半。 |
| 登記費用 | 登録免許税(固定資産評価額の0.4%など)、司法書士報酬(数万円~数十万円) | 原則として分割によって権利を取得する共有者。 |
その他の実務上の留意事項
- 登記手続き
共有物分割の合意ができた後、速やかに所有権移転登記や分筆登記などの登記手続きを行う必要があります。
これにより、法的に共有状態が解消されたことが第三者に対しても証明されます。
司法書士に依頼するのが一般的です。 - 境界確定
土地の現物分割を行う場合、隣接地との境界確定が必須となります。
測量士に依頼し、隣接地の所有者の立ち会いのもと境界を確認・確定します。
境界が不明確なままだと、将来的なトラブルの原因となります。 - ローン残債
共有不動産に住宅ローンなどのローン残債がある場合、金融機関の承諾なしに共有物分割を行うことはできません。
金融機関は、共有者の変更や担保物件の変更によって債権回収が困難になることを懸念するため、原則として一括返済を求められることが多いです。
新たな共有者がローンを引き継ぐ場合は、審査が必要となります。 - 共有者間の人間関係
共有物分割は、親族間など共有者間の人間関係に大きな影響を与える可能性があります。
感情的な対立が深まると、話し合いが困難になり、解決まで長期化することもあります。
専門家(弁護士など)に間に入ってもらうことで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進められる場合があります。 - 共有物分割禁止の特約
共有者間の合意により、5年を超えない期間で共有物分割をしない旨の特約(共有物分割禁止特約)を定めることができます。
この特約は登記することも可能で、登記すれば第三者に対しても対抗できます。
ただし、期間満了後は再度分割請求が可能となります。
共有物分割の典型的なケースと判例
共有物分割が必要になる典型的なケースは、相続による共有です。
遺言がない場合や、遺言があっても特定の相続人が不動産を単独で取得できない場合などに、相続人全員の共有状態となることがあります。
- 判例の傾向
裁判所は、共有物の性質や共有者の状況を総合的に考慮して、最も公平な分割方法を判断します。- 現物分割が困難な場合: 土地が狭小で分筆が非現実的であったり、建物が物理的に分割できなかったりする場合、代償分割や換価分割が選択されます。
- 全面的価格賠償の容認: 共有者の一人が居住している場合や、共有者の一人が単独で取得することを強く希望し、かつ他の共有者に代償金を支払う能力がある場合などには、全面的価格賠償が認められる傾向にあります。
例えば、共有者の一方が長年居住し、他方が遠方に住んでいるようなケースで、居住者がその不動産を単独で取得し、他の共有者に代償金を支払う判例が見られます。 - 連絡不能な共有者がいる場合: 共有者の行方が不明な場合でも、裁判所に共有物分割訴訟を提起し、公示送達の手続きを経て判決を得ることで分割が可能です。
この場合、行方不明の共有者には金銭的補償(代償金)が支払われる形になることが多いです。
まとめ
共有物分割は、複雑で専門的な知識を要する手続きです。
共有者間の協議で解決できるのが最も理想的ですが、困難な場合は弁護士や司法書士、税理士といった専門家のサポートが不可欠です。
特に、不動産評価、税金、登記手続き、そして共有者間の人間関係の調整など、多岐にわたる課題を解決するためには、早い段階で専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが、円滑な共有物分割を実現するための鍵となります。
共有物分割についてご不明な点がありましたら、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
大阪府下全域・関西エリアの不動産売却は「Go不動産(ゴーフドウサン)」にお任せください!
現地無料出張査定を実施しておりますので、どなたでも負担なく不動産の査定を受けていただくことが可能です。