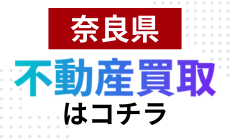遺留分(遺留分侵害)について
【相続トラブル】「遺留分」って何?知らないと損する最低限の権利
「うちは家族の仲が良いから、相続で揉めることなんてない」
「財産なんてほとんどないから、自分には関係ない」
多くの方がそう思っているかもしれません。
しかし、相続は誰にでも起こりうる身近な法律問題であり、思わぬところでトラブルに発展するケースは少なくありません。
特に、
「特定の相続人に全財産を譲る」
「お世話になった知人に財産をすべて遺贈する」
といった内容の遺言書が見つかったら、どうしますか?
「遺言だから仕方ない…」と諦めてしまうのは、まだ早いかもしれません。
法律は、のこされた家族の生活を守るため、相続人に「最低限の相続分」を保障する制度を設けています。
それが、この記事のテーマである「遺留分(いりゅうぶん)」です。
今回は、遺留分の基本から、権利を取り戻すための方法、注意点までの知識をまとめて紹介します。
そもそも「遺留分」とは?~最低限保障された相続の権利~
遺留分とは、一言でいえば「兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障された、最低限の財産の取り分」のことです。
故人(被相続人)は、原則として遺言によって自分の財産を誰に、どれだけ渡すかを自由に決めることができます。
しかし、その自由を認めすぎると、例えば「全財産を愛人に譲る」といった遺言によって、長年連れ添った配偶者や子供が路頭に迷ってしまうかもしれません。
そこで法律は、被相続人の意思を尊重しつつも、遺された家族の生活保障や、相続人間の公平を図るために、この遺留分という制度を設けているのです。
いわば、相続における「最後の砦」ともいえる権利です。
誰が権利を持っているのか?(遺留分権利者)
遺留分を請求できる権利(遺留分権利者)があるのは、以下の人たちです。
- 配偶者
- 子、またはその代襲相続人(子が亡くなっている場合は孫など)
- 直系尊属(父母や祖父母など) ※子がいない場合に相続人となります
ここで非常に重要なポイントは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないという点です。「兄である自分を差し置いて、全財産を甥に相続させる」という遺言があったとしても、兄は遺留分を請求することはできません。
どれくらいの割合がもらえるのか?(遺留分割合)
保障される遺留分の割合は、相続財産全体に対して、相続人の構成によって以下のように決まっています。
- 相続人が直系尊属(父母など)のみの場合:相続財産全体の3分の1
- 上記以外の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子など):相続財産全体の2分の1
この「全体の遺留分」を、法定相続分に応じて各相続人が分け合うことになります。
<具体例> 父が亡くなり、相続人が母と子2人(長男・次男)の場合
- 全体の遺留分: 相続財産全体の 2分の1
- 各人の遺留分:
- 母:全体の2分の1 × 1/2(法定相続分) = 相続財産の4分の1
- 長男:全体の2分の1 × 1/4(法定相続分) = 相続財産の8分の1
- 次男:全体の2分の1 × 1/4(法定相続分) = 相続財産の8分の1
もし父が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残していた場合、母と次男は、それぞれ自身の遺留分である4分の1と8分の1を侵害されていることになります。
「遺留分侵害」はどんなときに起こる?
遺留分が侵害されるのは、主に被相続人の遺言や生前贈与が原因です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 遺言による侵害
- 「長男に全財産を相続させる」
- 「内縁の妻に全ての不動産を遺贈する」
- 「特定のNPO法人に全財産を寄付する」
- 生前贈与による侵害
- 特定の子供にだけ、開業資金やマイホーム資金として多額の援助をしていた。
- 愛人にマンションを買い与えていた。
遺留分を計算する際の基礎となる財産には、相続開始時に残っていた財産だけでなく、相続人に対して相続開始前10年以内に行われた特別な生前贈与や、相続人以外に対して相続開始前1年以内に行われた贈与なども含まれます。
そのため、「財産は生前にほとんど贈与してしまったから、遺産はほとんどない」という言い分が通用しないケースもあります。
【重要】2019年法改正!「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ
2019年7月1日に相続に関する法律が大きく改正され、遺留分制度も大きく変わりました。この変更点は非常に重要なので、ぜひ押さえておきましょう。
- 旧制度:遺留分減殺(げんさい)請求 改正前は、侵害された遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求」という権利を行使していました。
これは、贈与や遺贈された財産そのものを取り戻す「現物返還」が原則でした。
しかし、この方法には大きな問題がありました。
例えば、不動産が遺贈された場合、この権利を行使すると不動産が複数の相続人の「共有」状態になってしまい、売却も活用もできず、かえって関係がこじれる原因となっていたのです。 - 新制度:遺留分侵害額請求 現在の制度では、権利の名前が「遺留分侵害額請求」に変わりました。
その名の通り、これは侵害された額に相当する金銭を請求する権利です。
つまり、「お金で解決する」のが原則になったのです。
これにより、不動産などを共有する複雑な事態を避け、スピーディーで柔軟な解決が可能になりました。
もし相手方がすぐにお金を用意できない場合でも、裁判所に申し立てることで、支払いに猶予期間を設けてもらう(期限許与)制度もできています。
遺留分を取り戻すための方法は?
では、実際に遺留分を請求するにはどうすればよいのでしょうか。手続きは以下のステップで進めるのが一般的です。
意思表示(内容証明郵便の活用)
まずは、財産を多く受け取った相手方に対して、「私は遺留分侵害額を請求します」という意思を明確に伝える必要があります。
口頭や普通の手紙でも可能ですが、後々のトラブルを避けるため、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の意思表示をしたか」を郵便局が証明してくれる「内容証明郵便」を利用するのが最も確実です。
当事者間での話し合い(交渉)
意思表示の後は、当事者間で具体的な金額や支払方法について話し合います。
ここで双方が合意できれば、最も円満かつ迅速な解決となります。合意した内容は、必ず「合意書」などの書面に残しておきましょう。
家庭裁判所での調停
話し合いがまとまらない、あるいは相手が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。
調停では、裁判官と民間の有識者で構成される調停委員が中立な立場で間に入り、双方の主張を聞きながら、解決案を提示するなどして、話し合いによる合意を目指します。
地方裁判所での訴訟
調停でも解決しない場合は、最終的に地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起することになります。
訴訟では、当事者の主張や証拠に基づき、裁判官が法的な判断を下します。
絶対に注意!遺留分侵害額請求の「時効」
遺留分侵害額請求権は、永遠に主張できるわけではありません。権利が消滅してしまう「時効」があり、この期間は非常に重要です。
- 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から「1年」
- 相続が開始した時から「10年」(除斥期間との考えあり)
特に注意すべきは「1年」という短い期間です。遺言書の内容を知るなどして、自分の遺留分が侵害されていると知った場合、そこからのんびりしている時間はありません。
この期間を過ぎてしまうと、たとえ権利があったとしても請求できなくなってしまいます。
遺留分の計算は複雑!専門家への相談が不可欠な理由
ここまで読んで、「自分でもできそう」と思われた方もいるかもしれません。
しかし、遺留分の請求、特にその前提となる侵害額の計算は、専門家でも慎重になるほど複雑です。
- 財産評価の難しさ:預貯金なら明確ですが、不動産や会社の株式などは、いつの時点で、どのような基準で評価するのかが非常に難しい問題です。
- 生前贈与の洗い出し:過去の生前贈与が「特別受益」にあたるのか、その証拠はどこにあるのかなどを個人で調査するのは困難を極めます。
「おかしいな」と思ったら、まずは一人で悩まず、相続問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
- 正確な遺留分侵害額の計算
- 内容証明郵便の作成や、相手方との交渉の代理
- 調停や訴訟になった場合の法的な手続きの全てを任せられる
- 相手方と直接やり取りする精神的な負担の軽減
- 最も重要な「時効」の管理を確実に行える
法律で認められた正当な権利を主張することは、決して悪いことではありません。
自身の権利を守り、悔いのない解決を迎えるためにも、遺留分という制度を正しく理解し、必要であれば専門家の力を借りて、最初の一歩を踏み出してみてください。
Go不動産では相続物件売却相談を承っております。
室内の片付けをせずとも、価格査定や、現金化が可能ですので、一度ご相談ください!