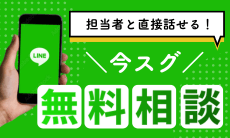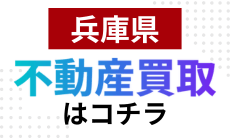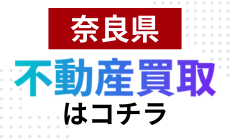特別受益のおはなし
【相続トラブル回避の鍵】
「特別受益」とは?生前贈与が相続分に与える影響を徹底解説
「うちの親はまだ元気だから、相続なんてまだまだ先の話」 そう思っている方も多いかもしれません。
しかし、相続は誰にでも必ず訪れる、とても身近な問題です。そして、いざその時を迎えると、「もっと早くから話し合っておけばよかった…」と後悔するケースが後を絶ちません。
特に、相続トラブルの火種になりやすいのが、「生前贈与」です。
「兄さんだけ、家を建てるときに親から多額の援助を受けていたはずだ」
「私は親の介護をずっとしてきたのに、妹は結婚祝いにたくさんのお金をもらっていた。不公平だ」
こうした不満が、遺産分割を複雑にし、家族の間に深い溝を作ってしまうことがあります。
今回の記事では、こうした相続人間の不公平をなくすための重要な法律上のルール、「特別受益」について、具体例を交えながら、基本的な考え方や計算方法、トラブルを避けるためのポイントなどを記載します。
そもそも「特別受益」って何?
「特別受益(とくべつじゅえき)」という言葉、なんだか難しそうに聞こえますよね。
でも、考え方はとてもシンプルです。
一言でいうと、「一部の相続人が、亡くなった方(被相続人)から生前に受け取っていた特別な利益」のことです。
例えば、相続人が子ども2人(長男・長女)だったとします。父親が亡くなる前に、長男だけマイホームの購入資金として1000万円を援助してもらっていたとしましょう。
この1000万円が「特別受益」にあたります。
もし、この1000万円を全く考慮せずに、残った遺産だけを長男と長女で半分に分けたらどうでしょうか?
長女は「お兄ちゃんだけずるい!不公平だ!」と感じるのが自然ですよね。
こうした不公平をなくし、相続人全員が納得のいく形で遺産を分けられるようにするのが、特別受益の制度の目的なのです。
法律(民法903条)では、特別受益にあたる生前贈与などがあった場合、その金額を相続財産に一度加算して(これを「持ち戻し」といいます)、その上で各相続人の取り分を計算し直す、と定められています。
つまり、特別受益は「遺産の前渡し」と捉え、その分を差し引いて最終的な相続分を調整する、というイメージです。
どんなものが「特別受益」になるの?具体例を見てみよう
では、具体的にどのようなものが「特別受益」と判断されるのでしょうか。
大きく分けて「遺贈」と「生前贈与」の2種類があります。
- 遺贈(いぞう) 遺言によって特定の相続人に財産を渡すことです。これは「遺産の先渡し」であることが明らかなので、原則としてすべて特別受益にあたります。
- 生前贈与 こちらが少し複雑ですが、ポイントは「遺産の先渡しといえるほど特別な贈与かどうか」です。以下のようなものが典型例です。
- 結婚・養子縁組のための贈与 結納金や持参金、嫁入り道具などで、親の資力や社会的地位から見て不相当に高額な場合、特別受益とみなされることがあります。
一般的なお祝い金の範囲であれば、特別受益にはあたりません。 - 事業を始めるための資金(開業資金) 子どもがお店を開く、会社を立ち上げる際に親が援助した資金などがこれにあたります。
- 住居に関する資金(マイホーム購入資金など) 家を建てるための頭金や、土地そのものを贈与された場合など、高額になりやすいため特別受益の典型例です。
- 高等教育の学費 ここが少し判断の難しいところです。
親には子どもを扶養する義務があるため、高校や大学の通常の学費は特別受益にあたらないことが多いです。
しかし、他の兄弟は高卒なのに一人だけ私立大学の医学部に進学し、そのために多額の学費援助を受けていた、といった兄弟間で著しい差がある場合は、特別受益と判断される可能性があります。 - 生命保険金 原則として、生命保険金は受取人固有の財産とされ、特別受益にはあたりません。
しかし、例外的に、保険金の額が遺産総額に対して非常に大きく、これを遺産分割の対象に含めないと著しく不公平になるような特殊なケースでは、特別受益に準ずるものとして扱われることがあります。
- 結婚・養子縁組のための贈与 結納金や持参金、嫁入り道具などで、親の資力や社会的地位から見て不相当に高額な場合、特別受益とみなされることがあります。
逆に、お小遣いやお年玉、通常の生活費の援助、一般的なお祝い金などは、扶養の範囲内とみなされ、特別受益にはあたらないとされています。
特別受益があると、相続分はどう変わるの?計算方法を解説
ここが一番のポイントです。
特別受益がある場合の遺産分割の計算方法を、具体例を使ってステップ・バイ・ステップで見ていきましょう。
【設例】
- 亡くなった人(被相続人):父
- 相続人:長男、長女の2人
- 父が残した遺産:3,000万円
- 生前贈与:長男がマイホーム購入資金として、父から1,000万円の援助を受けていた(これが特別受益)。
ステップ1:みなし相続財産を計算する
まず、相続が開始した時点の遺産に、特別受益の額を「持ち戻し」て合計します。これを「みなし相続財産」と呼びます。
計算式: 相続開始時の財産 + 特別受益の額 = みなし相続財産 3,000万円 + 1,000万円 = 4,000万円
ステップ2:各相続人の「一応の相続分」を計算する
次に、ステップ1で計算した「みなし相続財産」を、法定相続分(この場合は兄弟2人なので各1/2)で分けます。
計算式: みなし相続財産 × 法定相続分割合 = 一応の相続分
- 長男:
4,000万円 × 1/2 = 2,000万円 - 長女:
4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
ステップ3:特別受益を受けた人の最終的な相続分を計算する
最後に、特別受益を受けていた相続人の「一応の相続分」から、すでに受け取った特別受益の額を差し引きます。これが、その人の最終的な取り分となります。
計算式: 一応の相続分 – 特別受益の額 = 最終的な相続分
- 長男の最終的な相続分
2,000万円 - 1,000万円 = 1,000万円 - 長女の最終的な相続分 長女は特別受益を受けていないので、一応の相続分がそのまま最終的な相続分となります。
2,000万円
【結論】 このケースでは、最終的に長男が1,000万円、長女が2,000万円の遺産を相続することになります。
もし特別受益を考慮しなければ、残った遺産3,000万円を半分ずつ(1,500万円ずつ)分けることになり、長女にとっては不公平な結果になっていました。
特別受益の計算をすることで、公平な遺産分割が実現できるのです。
知っておきたい!特別受益の重要ルールと手続き
特別受益について、他にも知っておくべき重要なルールがあります。
持ち戻しの免除
これまで説明した計算(持ち戻し)は、原則的なルールです。
しかし、亡くなった方(被相続人)が
「この生前贈与は、遺産分割の計算に入れなくていいよ(持ち戻しをしなくていいよ)」
という意思表示をしていた場合は、その意思が尊重されます。
これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
トラブルを避けるためには、遺言書などで明確にその意思を残しておくことが重要です。
ちなみに、2019年の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の家やその購入資金を贈与した場合は、原則として「持ち戻し免除の意思表示」があったものと推定されることになりました。
これは、長年連れ添った配偶者の生活を保障するためのルールです。
特別受益の主張と証明
特別受益は、自動的に計算されるわけではありません。
「あの人には特別受益があるはずだ」と考える他の相続人が、遺産分割協議などの場で具体的に主張する必要があります。
そして、主張する側には証明責任があります。
「いつ、誰から、いくらの贈与があったのか」を、預金通帳の記録や契約書、メールなどの客観的な証拠を示して証明しなければなりません。
話し合いがまとまらない場合は?
相続人間の話し合い(遺産分割協議)で解決するのが一番ですが、意見が対立してまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停でも話がまとまらなければ、最終的には裁判官が判断を下す「遺産分割審判」へと移行します。
円満な相続のために今からできること
特別受益は、相続人間の公平を守るための非常に大切な制度です。
生前の何気ない援助が、将来の相続に大きな影響を与える可能性があることを、ぜひ覚えておいてください。
一番の相続トラブル対策は、家族間のコミュニケーションです。
親が元気なうちから、財産についてオープンに話し合ったり、なぜ特定の誰かに贈与をするのか、その想いを伝えたりしておくことが、将来の誤解や対立を防ぎます。
そして、財産を渡す側は、遺言書を作成し、「持ち戻し免除」の意思などを明確に記しておくことが、残された家族を守る最善の方法の一つです。
相続は「争続」ではありません。
家族の絆を壊さないためにも、正しい知識を身につけ、早めに準備を始めることが大切です。
もし少しでも不安な点があれば、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
大阪府下の買取り物件募集中です!
大阪市内・堺市内はもちろん
吹田市・高槻市・島本町・箕面市・池田市・豊中市・茨木市・摂津市・守口市・寝屋川市・門真市・枚方市・交野市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・松原市・忠岡町・高石市・和泉市・泉大津市・羽曳野市・柏原市・藤井寺市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・岬町
上記各エリアに無料出張査定を実施しております!
ボロボロの戸建て、雨漏り、床の腐食、シロアリ被害、家具や家電がそのままになった物件などでも問題ありません
ぜひ「Go(ごー)不動産」にご連絡ください!